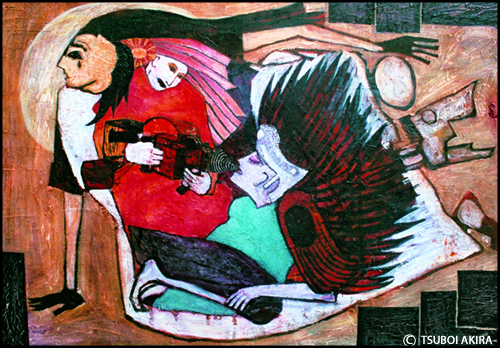
「ドリル」
1300×920mm
2004
「『アメリカ同時テロ』。」
「『貿易ビル・国防総省にハイジャック機突入』。」
デイルームと言われた施設の居間で、
車いすに乗ってみうごきのとれなくなった昔教師をしていた男の脇にいて
その日の新聞をひとり、読み聞かせていた時期がある。
「オザワさん、昨日ですね。
アメリカ、ニューヨークの世界貿易センタービルという巨大なビルに、
旅客機がハイジャックされてですね」
「なんと、その旅客機がそのビルに突っ込みました。」
「ははは。」
男性は、
そのニュースが凶報であれ、吉報であれ、読み聞かせると笑った。
理由はわからなかった。
色の白い、なめらかな肌をして、めがねをかけていた。
横たわったベッド上の彼を車いすに移す時、
白い一個の川石を見詰めるように思っていた。
年老いて、痴呆が進行していたらしいが、
日々のなかで、ごくわずかに交わす受け答えに破綻はなくて、
込み入ったことを応えようとは思うのだが、
余力が続かない。
言おうと思うことを言いきるなかばまでたどり着かず、
思いは統合の力を喪って、霧散してしまう、
そんな感じだった。
「それでですね、実はそれが手始めで」
「それを機に、ワシントンの国防総省、ペンシルベニアへ
同じようにハイジャックされた旅客機がつぎつぎと突っ込だと書いてあります。」
「がはは。」
「それで、その数週間前にイスラム過激派の国際テロ組織、
アル・カーイダのオサマ・ビン・ラディンという
男が大規模テロを予告してたらしく、」
「今、そのビン・ラディンについての報道がさかんになってます。」
「オザワさん、」
「その模様が、ほとんど生中継でテレビで報道されたんですよ。」
午前中の
わずかに眠気のただようデイルームに二人の声が響く。
「そ、そ、それは、あれかね。
アメリカの、だ、大統領のあ、あれかね。」
「大統領の、」
「大統領の。」
そこでオザワさんの言葉は止まってしまう。
オザワさんは社会の教師をしていた。
本を読むのが趣味で、生涯独身だった。
年老いてから
認知症を発症して、その都心の施設に入っていた。
入所当初は杖をついて歩いていたが
六年がたっていたその時にはほぼ寝たきりになり、
レーシングカーのシートのような、
関節ごとに調整が利く質の良いクッションが取り付けられた
リクライニング式の車椅子に乗せられるようになっていた。
度の強い眼鏡をしていて、
口数のすくないおだやかな男だった。
オザワさんの介護方針を組んでいたのが
同じく眼鏡をかけた色の白い、機械いじりの好きなハヤシという介護職員で、
新聞を購読し続けることもこの聡明で、清潔なおとこが決めていたのだった。
「ツボイくん、なにしてんの。」
「いや、オザワさんに新聞を読み聞かせているんですよ。」
「ねえ、オザワさん。」
「はは、はははは。」
オザワさんは傾いた顔で、笑った。
「いいね。」
ハヤシには、多くのことを教えてもらった。
惰性に流れがちの日々の中で、
まだ介護をやりたての頃、
ある老女の飯におもむろに薬をかけてまぜて食わせていた。
それは独断でおこなっていたことではなくて、慣習のようにみなが行っていたことだった。
「ツボイくん、」
「おかずに薬をまぜるな。」
ハヤシが脇に立って言った。
真剣な怒りを発していた。
「そんな薬まみれの飯を、自分で食うのか。」
「冷蔵庫に小さなゼリーがある。」
「そこに薬をまぜて、すこしずつ食べさせて。」
「ゼリー持ってきて。」
じぶんは恥じ入って、ほんの小さなゼリーを持ってきた。
「いいか。」
「こうやって。」
ハヤシは、きんぴらの上に白くまぶされた薬の粉をスプーンで取り除き、
小皿に取ったゼリーとまぜて、口の利けなくなった老女の口に持っていった。
「イノセさん、おくすりですよ。」
「ツボイくん、惰性で薬を飯にまぜて平気で食わせるような人間になったら、終わりだよ。」
「無感覚になるな。」
ハヤシは振りむいて自分に言った。
「ツボイくん、ところでちょっと聞きたいんだけどさ。」
オザワさんの脇でハヤシが言った。
「なんでもいいから思いつく四字熟語言ってみて。」
「四字熟語、ですか。」
「そう。考えちゃだめ。」
自分は
「豪華絢爛。」
「比翼連理。」
言った。
「なんだその、ヒヨクレンリってのは。」
「まあ、仲の良い夫婦、女と男のことですよ。」
「へええ、むずかしい言葉知ってんねえ。」
ハヤシは顔をまげて言った。
「なんでですか。」
「いや、昨日飲み会でさ、」
「こうやっていきなり言いだした四字熟語にそいつのほんとの考えてることがでるって看護婦が言っててさ。」
「へええ。」
「ハヤシさんは何をいったんですか。」
「それは、いいよ。」
「新聞読むの、続けてよ。」
「よかったですね、オザワさん。」
ハヤシは後方で彼が趣味でやっていたバイクの修繕の話を、
同僚の修繕を頼んだ男とし始めた。
比翼連理。
ハヤシには妻があって、
おなじ施設の厨房で毎日年寄りの飯を作っていた。
色の白い、背の高い成熟した女性で、
白い花をむすぶ木蓮のような印象をもたせる美貌だった。
ここに来る前には画廊の喫茶店で働いていたらしく、
じぶんが行った個展に、手作りのクッキーを入れて持ってきてくれたことがあった。
たまに厨房からなにか物をとりにやって来ると、
彼女の美貌に幾度となく顔を見合わせているはずなのに、
入居者のいわき出身の老女が美人が来た、と言って毎度おどろくのだった。
ハヤシは心底この年上の木蓮のような女に惚れて、
結婚した。
子は、ハヤシが嫌いだから作らない、と言っていた。
「オザワさん、今アメリカの大統領はブッシュって言うんですよ。」
「そうか。」
「ちょっとヤクルト飲みましょうか。」
自分はまた、新聞を読み始めた。
分にしておよそ長くても4、5分。
ほかの介助の必要な入居者に、
水分補給をしなければならない。
施設での介護は、もろもろの仕事が詰め込まれて、なかなかに時間がなかった。
短い間に、そんな笑い話をして、
新聞を開いてオザワさんに手渡す。
車椅子のクッションに取り囲まれて、
開かれた新聞を両手で捧げ持って
オザワさんは同じページを
じっと見つめるのだった。
その新聞は、
それまでは、そんなふうに読まれることはなかった。
朝、貧相な若い警備員が
ケアテーションにその日の新聞を置いてゆくと、
職員のリーダー的な存在のタドコロが、
仕事の手のあいた時に一服しながら読み、
広告はゴミ箱へ、
読んだ新聞は
そのままオザワさんのベッドの脇にある新聞を捨てる箱に入れられ、
オザワさんの手に渡ることはなかった。
食事ごとにベッドから車椅子に乗せられ、
デイルームに運ばれ、
食事をとり、歯をみがき、
ベッドへと戻る。
その歯車のような繰り返しの日常のなかで、
オザワさんが食事時に
「あつい。」
「つめたい。」
「にがい。」
と即物的に反応をもらす以外の言葉を
それまでオザワさんから聞いたことがなかった。
スプーンを持つことがむずかしくなり、
通常の車椅子では姿勢を保持することがむずかしくなる、
年をおって進んでいったオザワさんの衰えに、
新聞を読む力はもはやないだろう、
おそらくは口にせずとも職員は思っていたのであろう。
結局、
新聞は
オザワさんの手に渡ることはなく、
日ごと無為に職員に読み捨てられるようになっていた。
ハヤシもそうして新聞をなかば捨てる側に入っていて、
内心には忸怩とした気持ちを抱え込んでいたのかもしれない。
「おれの母さんも、絵を描いていたんだよ。」
いつしかハヤシが言っていた。
「だからおれも小さいころから絵をよく見せられてね。」
「おれは、ジョージア・オキーフの絵が好きなんだ。」
オキーフの、どこかプラスチックのような質感の向日葵の絵を自分は思いだしていた。
「おれは、おやじがいなくてね。」
「母さんが年取ったときに、介護しなきゃいけなくなった時に」
「尻を拭いたりするのが仕事としてできるようになりたくてこの仕事をはじめたんだ。」
「仕事としてなれちまえば、」
「なにも思わなくて済むんじゃないかと思ってさ。」
バイクいじりが好きで、
アメリカまで工具を買いにゆくハヤシの周りには
ただで修繕してくれるというので多くの同僚が集まってきていた。
多くの惰性のなかで生きる個性に好意をもって取り囲まれて
ハヤシは独自の居場所は築いていたけれども、
ハヤシが根に息づかせている無垢な清潔さは
惰性の大勢に流されて発露する場を喪っているように見えた。
孤立を常にしていた自分になにか共鳴をするものを感じたのか、
自分のあまりにもまとめることのできない孤立を冷やかしながらも
ハヤシはそんな思いをじぶんに伝えることがあった。
いつものように
タドコロが新聞をステーションで読んでいた。
そうして新聞の読み聞かせをはじめた翌日、
時間がないので、自分は時計を見ながら読み終わるのを待っていた。
なかなか終わらないので
「タドコロさん、その新聞、こっちにくれませんか。」
言った。
「ちょっと、待ってて。」
タドコロは言った。
自分は立っていた。
なかなか終わらない。
「おい、」
「はやくしろよ。」
自分は言った。
「おまえの新聞じゃないんだよ。」
自分が言うと、おどろいた顔で
「おまえ、だと-」
タドコロが色をなした。
「おまえ、年上の人間にむかってなんて口の利き方するんだ。」
「いいからはやく、よこせよ。」
「それはオザワさんの金で買ったもんなんだよ。」
「おまえの物じゃねえんだよ。」
「オザワさんに読んで聞かせるんだ」
「時間がないんだよ。」
「おまえが捨てるためにあるんじゃねえんだよ。」
自分が地金を現わして言うと、タドコロは逆上した。
「ぐちゃくちゃうるせえこと言いやがって」
「この、きちがいが。」
「ああ、そうだよ。」
「おれは、」
「狂ってるんだ-。」
「そんなことはどうでもいいから、早くよこせよ。」
自分が言うと、タドコロは
「めんどくせえ。」
「ほらよ。」
新聞を投げてよこした。
自分は、新聞を拾って持っていった。
その日、ハヤシの奥さんが倒れていた。
脳出血らしかった。
すぐに病院に運んだらしいが、運んだ先の病院は衛生管理がずさんで、
医療器具からの感染症で患者が死ぬニュースが流れた。
それから、
ハヤシはさかんに酒を飲むようになって、
押し寄せる鬱屈を酒勢で散らすようになった。
「オザワさん、」
「中学三年の時、不登校だった子の6割は働いて」
「3割は高校とか学校に行ってるらしいです。」
「オザワさんの生徒はどうでした?」
その日の見出しを見て言うと、
目をしばたいていたオザワさんは
「がっははは。」
おおきな声で笑った。
「そ、そ、そうだねえ」
「そうだねえ。」
しばらくして言った。
「ふ、不登校の子は、い、いなかったな。」
活きた言葉だった。
「嫁さんうしろに乗せて、」
「いろんなところへ行くんだよ。」
「会津にも行ったよ。」
「五色沼を見にね。」
ハヤシが、いつか言っていた。
山間の田園の道を、美貌の二人が走ってゆく。
ひとはいなくて、
ハヤシの奥さんはヘルメットを外し、
色の入っていない長い髪を草の匂いのする風の中に晒し、
ゆったりと任せる。
ハヤシはヘルメットをしたまま、そこまで飛ばさずにバイクを走らせる。
奥さんはハヤシの胴にまわした腕を、ひとつつよく抱きしめ、
ハヤシの顔を覗きこんだ。
すこしはなれた所から覗かれ、俯瞰に移ってゆくその遠景を、
奇跡的に現実に結晶した夢のかけらのように、
幻視したことを覚えている。